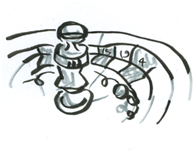アレア(偶然)
スポーツは「賭け」である
──「偶然」の問題に触発されて
稲垣正浩(「ISC・21」主幹研究員)
宗教では、一般的に、「偶然」は認めない。「奇跡」や「秘跡」は認めるが「偶然」は認めない。だから、賭け事を宗教は認め
ようとはしない。しかし、わたしたちが生きている実感としては「偶然」だらけであるし、人生そのものがある種の「賭け」ではないかとおもうこともしばしばである。逆に「賭け」のある人生は、少々の危険を度外視すれば、楽しいし、充実していることは間
違いない。むしろ、「賭け」は人生の味付けとしては必要不可欠のものですらある、と。
こんなことを、まず、ぼんやりと考えている。
つまり、「偶然」に「賭ける」ということは、じつはとても大事なことなのに、なぜか、これを敵視する見方・考え方が強い。たぶん、「偶然」や「賭け」を無制限に容認してしまうと、いろいろと実生活の上で不都合が生じてきてしまうからなのだろう。だから、公的な場面では、ある規制がかかる。その分、裏にまわって、こっそり私的に楽しむ、ということが起こってくるのだろう。
宗教上の教義は、いってみれば近代社会の「法律」にも相当する、前近代に生きる人びとの「規律」を示していたのだろう。つまり、法律のない時代にあっては、悪いことをする人間の「歯止め」として宗教がその役割をはたしていたのだろう。だから、「たまたまそうなったのだ」という「偶然」を装ういいわけを許すことはできなかったに違いない。だから、一つの考え方として、宗教的には「偶然」というものは存在しない、と教え諭したのだろう。で、問題はここから。しかし、人間は、自分の理性で考えて納得できないことは「神さま」のせいにしたり、 「縁起」 (「因縁」)のせいにしたりして、一応の納得(気持ちの整理)をしてきたのではないか。つまり、自分の力の及ばざるところの問題は、すべて「まったき他者」(神,仏,縁起,超越,など)にゆだねて、それなりに「折り合い」のつけ方をしてきたのではないか。別の言い方をすれば「苦しいときの神頼み」ということになろう。この「他者」に身(自己)をゆだねる、というところにカイヨワのいう「偶然」(アレア)を考える重要な鍵がある、とわたしは考えている。
たとえば、ルーレット。1から36までの数字にOを加えて、全部で37枠(アメリカでは00が加わるので38枠)。つまり、確率論でいえば、37分の1の確率で当たることになる(ただし、Oは親のアドバンテージ)。で、ルーレットの方法論(戦術など)については省略することにして(詳しくは、檜垣立哉著『賭博/偶然の哲学』)、いろいろに考えた上で、いずれかの数字に賭けることになる。直感もふくめて、作戦を考えるところまでは、自己の問題である。しかし、賭けが決まってチップを台に乗せたあとは、もはや、自己の出番はない。どうするか。運を天にまかせるしかない。つまりは「神頼み」。自己を放棄して他者にすがるのみ。この自己の枠組みの<外>に自己を投げ出すこと、ここに「すべて」がある。
この構造は、じつは、信仰の世界に飛び込むこととそっくりではないか。つまり、「偶然」 という賭けごとに身をゆだねるという
ことは、その根拠は別として、「神さま・仏さま」に身もこころも投げ出すのと同じだということ。しかも、 根本的に違うところは、神さまも仏さまも「偶然」の賭けごとを許してはくれないということはわかっているのだから、純粋に「偶然」の賭けごとに身をゆだねるということは、とんでもなく孤独な、虚無の世界に身をゆだねるにも等しい経験となる。バタイユがいうところの 「信仰なきエクスターズ 」の、地獄に落ちていくような恐怖の、よるべなき強度につながっていく。だからこそ、ここに「すべて」があるのだ。
禅的にいえば「百尺竿頭一歩を出」という経験にも等しい。無の世界に一歩を踏み出せ、というのだ。そこは、バタイユのいう「信仰なきエクスターズ」ともまったく異なる別世界。しかし、きわめて近い世界(である、とわたしは考えている)。すなわち、「知」の機能しない「非-知」の世界。禅では「大死」という。一度、死んでしまえ。そうすれば怖いものはなくなる。生にこだわるから俗から離れることはできないのだ、と教える。カイヨワの思考はこのあたりまで伸びていて、その上で、「偶然」(アレア)の問題を遊びの四つのカテゴリーの一つとして位置づけている、とわたしは考える。
スポーツは「賭け」である。勝つか負けるかはやってみなければわからない。これはスポーツが成立するための前提条件である。
このように書くと、ただちに、勝ち負けと関係のないスポーツもある、という反論がでてくるだろう。そんなことは百も承知で書いている。ここでいうスポーツは、ごく一般的な近代競技スポーツのことを念頭におき、とりあえずは、ごく一般論として考えてみよう、という次第。
スポーツは「賭け」である、というテーゼを立てるということの意味は、スポーツには「偶然」(あるいは「偶然性」)が多く含まれているということを前提にして、もう一度、スポーツとはなにか、を考えてみようというところにある。この小論でどこまで可能かは不明であるが、とにかく行けるところまで行ってみよう。
そのむかし、イギリスで競馬が盛んに行われるようになった初期のころ、ある特定の馬が連戦連勝することがあって、競馬の賭けが面白くなくなり、急速に客足が遠のいてしまったことがある。このとき、ある知恵者が現れて、ハンディキャップなる制度を提案した。 つまり、 勝ってばかりいる強い馬の背中にある一定の重さの「砂袋」を乗せて走るというハンディを負わせることによって、勝負結果の予測を不可能にする、つまり、勝負結果を混沌状態にする、というアイディアである。それがこんにちの「ハンディ」と呼ばれる制度の発端である。この制度がいかに有効であったかは、こんにちにいたるまで大切に維持されていることをみれば明らかである。つまり、「偶然」の要素を意図的(人為的)に盛り込んだというわけだ。
ただし、この競馬の例はきわめて例外的なものと考えるべきであろう。スポーツの勝敗を決する最大の根拠は「実力」である。どれだけのきびしい修練を積んで、アスリートとしての「力」を蓄えることができたか、がまずは大前提となる。 その上で、 コンディショニングの調整、気候条件、集中力、冷静な判断力、情緒的安定、勝負の駆け引き、などなどもろもろの条件が重なって、実際の勝負の結果が生まれてくる。そうしたことがらに万全を期して、完璧な準備を整えたにもかかわらず、まったく予期せざる突然の「身体の反乱」が起こったりすることがある。だからこそ、スポーツは面白いのである。つまり、スポーツには「偶然」が呼び出される「隙間」があちこちに仕掛けられているのだ。この「偶然性」が多ければ多いほど勝負の結果を混沌状態にさせる。すなわち、なにが起こるかわからない。胸がときめくのは、こういうときだ。
ようやく寝不足から解放されてやれやれとおもっている人も多いであろうサッカーW杯のにわか応援団にとっても同じだ。サムライ・ブルーが予選リーグを勝ちぬく「確率」はきわめて低かった。戦前の予想ではほとんど絶望視されていた。ところが、予想に反して、カメルーンに勝った日本チームは一気に息を吹き返した。見違えるようなチームに一変した。オランダには負けたけれども善戦した。その勢いを維持してデンマークには予想外の勝ち方をした。こうなると、ひょっとしたら、という期待値がにわかに高まり、二匹目のどじょうを狙うようになる。しかし、最後のベスト・エイト進出をかけた試合は、延長線にもつれこみ、それでも勝敗を決することができず、ついに、PK戦で敗退となる。これを「弱気の虫」がでたとみるか、「偶然」とみるか、いずれにしてもやってみなければわからないから、ハラハラドキドキする。だから、面白い。
スポーツは「賭け」である、 ということを考える事例としては申し分のないタイミングだった。「偶然」 という「隙間」があちこちに仕掛けられている・・・だからこそサッカーは面白いのだろう。そして、この「偶然」を呼び込む「運の強さ」もまたついてまわる。
それが、ほんの一瞬の 「隙間」 をついて立ち現れる。信じられないようなスーパー・プレイが生まれる。人びとは、そこに「神の降臨」をみる。全身が打ち震えるような感動の一瞬である。
人事をつくして天命を待つ、ということばがある。 人事を超越したところで起こる現象は、すべて 「神事 」であり、「神の領域」のものとしてみずからを納得させる。もっとも、「偶然」を呼び込むのも「実力」のうち、という考え方もある。しかし、そこでいう「偶然」は人事と神事の中間領域に発生するレベルのことであって、「偶然」のすべてを言い当てているわけではない。だから、最終的には「 偶然」は「神頼み 」であり、「神の領域」のものである、といわざるをえない。したがって、この「偶然」に「賭ける」という人間の営みは、じつは「神事」なのである。すなわち、これこそが「正義」。
スポーツの淵源は、こうして、ついには「神事」にたどりつく。つまり、勝つか、負けるか、はやってみなければわからない。すなわち、スポーツは「 賭け 」である。その「賭け」の世界をしはいしているのは「神」。だから、「賭け」は「正義」なのだ。古代オリンピアの祭典競技は、その典型的な事例と考えてよい。この時代の人びとは、競技の結果はすべて「神」が決定すると信じていた。だから、「神」に供犠をささげ、必勝祈願を全身全霊をこめておこなった。しかし、神話的コスモロジーがしだいに後退し、ギリシア哲学が台頭するにつれ、古代オリンピア祭の「世俗化」が進展し、やがては本格的な「プロ選手」の登場となる。そうして、「神事」としての競技は没落の一途をたどることになる。しかも、皮肉なことに、古代オリンピア祭にたいして最後のとどめを刺したのは、ローマのキリスト教である。
現代のスポーツ競技はその延長線上にある。「 偶然 」を科学の力で否定し、競技を「神の領域」から引きずり降ろし、ついには「神事」から「人事」の占有物にしようと企む。その頂点に立つものが「ドーピング」である。つまり、「アンチ・ドーピング」運動の背景には徹底した「偶然性」排除の思想がある。もっと言ってしまえば、「神」を否定して、その代わりに「科学」を君臨させようという思想である。すなわち、「 科学 」という名の新しい「宗教」の誕生をそこに見届けることができる。そうして、あってはならない新規の「正義」が登場することになる。神の名を騙る「正義」である。こうして、「ラプラスの悪魔」はますます力をたくわえ、世界制覇に向けて疾走する。
世界は「 偶然」に満ち満ちているからこそ面白い、とわたしは考える。「偶然」に満ち満ちているからこそ「 賭け」(ここでは「正義」そのものの意)が成立する。だから、人生は面白い。「偶然」が皆無になってしまった人生など生きるに値しない。ファウスト博士が「永遠の命」と引き換えに、自分の「魂」を売り飛ばしてしまった結果、そのさきには「絶望」しかなかった話を想起すれば十分だろう。
人生には「未知」の世界が待っている。だから、生きるに値する、と。「未知」の世界とは、まさに「偶然」に満ち満ちた世界そのものだ。そこには、夢も希望もいっぱいだ。生きてみないとわからない「未来」がある。だから、人生もまた立派な「賭け」なのである。スポーツは人生そのものなのだ。
サッカーのW杯の年になると、日本国民の大半が、いや、世界中のW杯にチームを送り込んだ国の人間の圧倒的多数が、にわかに「熱狂」する。その「熱狂」ぶりは他に例をみないほどだ。オリンピックやその他の競技種目のW杯とも比較にならない。なぜか。それにはいろいろの理由があろう。それについては、いつか、稿をあらためてきちんとした分析をしてみたいとおもう。が、ここでは、「偶然」との絡みで、ごく簡単にその一端に触れておこう。
「熱狂」する人びとは、みずからの人生の写し鏡(あるいは、代替物)としてサッカーと相対しているのではなかろうか。もっと言ってしまえば、みずからの人生に「欠落」してしまった「偶然」の具現を見届けようとしているのではなかろうか。もっと踏み込んでおこう。みずからの枯渇してしまった「生の淵源」に触れる機会を待ち望んでいるのではなかろうか、と。だとすれば、「偶然」に「賭ける」ということは、「偶然」に「触れる」という経験への期待であり、それはそのまま「神の領域」への接近を意味し、もし、可能であれば「勝利の女神」と「合体」することを夢見ているに等しい。
断るまでもなく、それは自己の<外>に身を投げ出す経験であり、絶対的なる「他者」との「合体」をめざす。現代社会に生きる人間の、圧倒的な「欠落」を補填する営み、そんな文化装置がサッカーには秘められているのではないか。その決定的な鍵を握っているものこそ「偶然」という「神の領域」の占有物ではないか。その「神の領域」の占有物である「偶然」を、全身全霊をこめて現世に引きずり出すこと、それこそが「サポーター」と呼ばれる人びとの「生きがい」そのものではないか。この種の「熱狂」、あるいは「祝祭空間」の復権に、 多くの「 にわかサポーター」たちを巻き込む「力」がサッカーには秘められているのではないか。
その淵源をたどっていくと、そこには「ヒト」が「人間」になるときに失った「内在性」への回帰願望がある、とわたしは考えている。すなわち、「偶然」に満ち満ちた「神」の世界への回帰願望が・・・・。