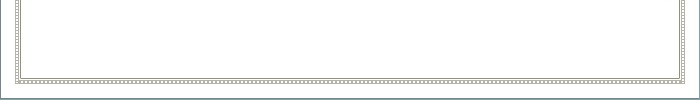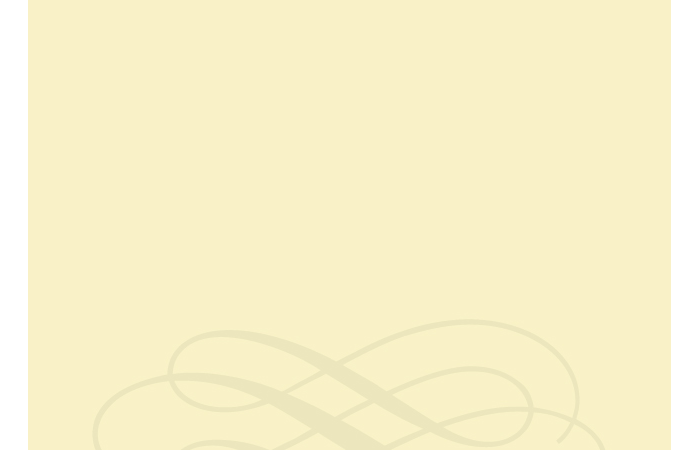今月のことば
2008.8

老子『道徳経』第1章を読む
太極拳のことを考えていると,その思想的な背景の一つとなっている老子の思想にたどりつく。
だから,何回もそのテクストである『老子道徳経』を読みなおすことになる。これまで,何回,それを
繰り返してきたことか。しかも,第1章をどう読むかが問題となる。すなわち,「道」なるものの原イ
メージをどのように描くか,という点である。これについては,これまでにもいくつもの解釈があって,
どれも,いま一つわたしには納得できない。もう,そろそろ自分なりの読解を試みて,それを文章に
して,対象化することを試みてもいいか,と思いはじめた。その試みの第一弾がこれである。つたな
い文章にすぎないが,みずからをさらけ出して,みなさんの忌憚のないご批判を仰ぐことによって,
もう一つさきに進みたいと熱望する。
第1章
〔原文〕
道可道、非常道、名可名、非常名、無名、天地之始、有名、万物之母、故常無欲、以観其妙、
常有欲、以観其キョウ、此両者、同出而異名、同謂之玄、玄之又玄、衆妙之門、
〔意訳文〕
もし,「道」というものが説明できるものであるとしたら,それは永久不変の,真実の「道」ではな
い。つまり,「道」というものはことばに置き換えることのできないものなのだ。「名」もまた名前をつ
けることができるものであるとしたら,それもまた永久不変の,ほんとうの「名」ではない。つまり,
「名」というものは仮の名前にすぎないものなのだ。天と地が現れたのは「名づけることのできな
いもの」から,すなわち「無名」からであった。つまり,天と地にも,最初は名前はなかったのだ。し
かし,名前をつけることによって,そのものの概念が定まり,共通の理解をえることができるよう
になったのだ。だから,「名づけることのできるもの」,すなわち「有名」は,あらゆる物を育てる母
にすぎない,ということになる。ここから,また,新たな「欲望」というものが立ち現れ,わたしたち
のものごとをみる目を狂わせてしまう。したがって,「ほんとうに欲望から解き放たれた者のみが
『妙』(かくされた本質)をみることができるのであって,欲望にとらわれている者はどんなことが
あっても『キョウ』(その結果)しかみることができない」のだ。この「妙」と「キョウ」の二つは,もと
もとの出所は同じであるけれども,名は違う。このもともとの出所のことを,われわれは「玄」(神
秘)と呼ぶ。もっと厳密に言えば,「玄」(神秘)よりももっと「見えにくいもの」というべきだろう。
つまり,もともとの出所は,ほんとうにぼんやりしていて,はっきりとは見えないもの,なのだ。し
かも,そここそが,あらゆる「妙」(かくされた本質)が立ち現れてくる「門」なのである。しかも,
その「門」には構えがなく,360度,あらゆる方向を向いている。だから,「妙」(かくされた本質)
はどこからでもやってくる。
この意訳文に到達するまでにわたしの脳裏をよぎって行ったものは、西田幾多郎の「実在」の
考え方であり,その背景をなしている禅の「無」であり,龍樹の「空」の考え方である。同時に,
『老子化胡経』(仏教は老子に帰すと主張する経典)の存在も意識して,仏教との近似性をも視
野に入れる。老子の言う「玄」は,ここでは小川環樹のいう「神秘」という解釈をとった。が,一般
的には「混沌」とされる。この説にしたがえば,「混沌のまた混沌」,あるいは,「混沌のもっともっと
混沌としたもの」(「玄之又玄」)ということを突き詰めていくと,おそらく「つかみどころのない,ぼ
んやりしたもの」「はっきりとは見えないもの」となっていく。そして,さらに「玄之又玄」を繰り返し
ていくと,その先にはなぜか澄みきった「透明なもの」のイメージが立ち現れてくるように思う。
つまり,「無」や「空」と同じところに到達する。そここそが「実在」の「場」であると西田は考える。
ここはことばで説明することはできない,と歴代の禅僧たちは説いている。老子の言う「道」と
同じである。
西田は,これらの「無」「空」「道」「玄」を西洋の哲学(すなわち,形而上学)のことばで説明す
べく全力を傾ける。そして,「実在」をてがかりにして,「場所の論理」「行為的直観」「絶対矛盾
的自己同一」へと思考を進化させている。この世界と,ジョルジュ・バタイユのいう「非─知」(ノ
ン・サヴォワール)とは,とても近いとわたしは考えている。たとえば,バタイユの言う「エクス
ターズ」(恍惚)と「絶対矛盾的自己同一」との違いは,無神論の立場に立つ「エクスターズ」
か,それとも禅仏教の説く「禅定」の境地に立つ「恍惚」か,でしかない。しかも,そここそが老子
の「玄」であり,「衆妙之門」となる。
そこには,しかし,自己は存在していない。自己が立ち現れるのは「他者からの働きかけ」によ
る。この自己が立ち現れる瞬間を,ジャン=リュック・ナンシーは「パルタージュ」という概念をもち
いて説明する。すなわち,他者との「接触」による「分割/分有」という現象である。ここがまた,
老子の説く「衆妙之門」ともつながっていく。つまり,自己もなにもない存在から他者との「接触」
をとおして自己が立ち現れるこの瞬間こそが「衆妙之門」とつながっていく。このとき,「欲望」と
いうものとの距離に応じて,「妙」に至るか,それとも「キョウ」に傾くか,という問題が生まれてく
る。
「大道無門」ということばがある。一般的には,「大きな道には門はない」,すなわち,「芸能や
芸道で大成するには方法にこだわるな」と解釈されている。もっと意訳しておけば,大きな目的
を達成するためには自由自在に智慧をはたらかせてあらゆる方法を用いよ,となろうか。ある
いは,「大道」とは「大きな道」,すなわち,「大きなタオ」。そこには「門」は建てようがない。そこ
に到達することこそが「衆妙之門」か。
〔註記〕
文中に「キョウ」とあるは,パソコンで探しても見つからない文字。「檄」という文字の木偏のと
ころが行人偏になっている文字。